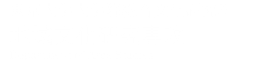報告
第29回 公開シンポジウム
いま「暴力」を考える
日時: 2021年6月26日(土) 14:00-17:30
会場: オンライン(ZoomWebinar)
専攻長挨拶:森井裕一
趣旨説明:藤岡俊博
地域文化研究専攻では、世界のさまざまな地域や時代を各自の人文・社会科学の専門分野の立場から研究するスタッフの多様性を活かし、横断的・越境的なテーマを取り上げてシンポジウムを開催してきました。今年度は「暴力」を中心テーマとし、とりわけこの数年来、各地域で現れている「暴力」の位相を、フランス・香港・アメリカの事例をもとに考察しました。
今日、私たちは、日常的にあらゆる種類の「暴力」に直面しています。「暴力」には、殺人や暴行のように生命を脅かす物理的なものもあれば、ハラスメントやヘイトクライムのように身体への直接的な働きかけを含まないものもあります。また、法や制度を介したシステム的な権力も、個人や集団に対する「暴力」の役割を演じることがあります。「暴力」それ自体はつねに人間社会に存在してきたと言えますが、今日の「暴力」を考えるうえでの大きな変化として、「暴力」の可視性が急速に拡大していることが挙げられます。誰もがスマートフォンで簡単に写真や動画を撮ることができるようになり、「暴力」が振るわれている現場の映像がSNSを通じて世界中に拡散されています。注意すべきなのは、このように可視化されて拡散される身体的なわかりやすい「暴力」のイメージの背後には、その地域や社会に特有の歴史や文化、異なる権力や対立の構造が存在しており、こうした言わば不可視の「暴力」の堆積が、ときに一人の個人の身体に凝縮して現れている点です。
今回のシンポジウムでは、フランス・香港・アメリカでの最近の事例にもとづきながら、こうした「暴力」の背景にある歴史的・社会的構造をめぐって議論がなされました。
報告1「現代フランスにおける暴力の諸相――ライシテの転機に」
伊達聖伸 (地域文化研究専攻)
報告2「『見える』暴力と『見えない』暴力――2019年大規模抗議活動以降の香港」
谷垣真理子(地域文化研究専攻)
報告3「暴力と非暴力のアメリカ」
矢口祐人(地域文化研究専攻[情報学環])
報告1(伊達聖伸)では、イスラームのジハード主義者によるテロリズム、「黄色いベスト」運動、カトリック聖職者の小児性愛というフランスの「暴力」の三つの事例を取り上げ、ライシテの確立期にあたる第三共和政前期の状況を歴史的な補助線として引きながら、当時の政治と宗教の権力関係および経済・社会問題を鏡として現代の「暴力」を映し出す試みがなされました。宗教批判を通してみずからの正統性を獲得してきた政治権力が現在ではイスラームに対して同じ図式を反復していること、旧来の労働組合が対応できない新たな階級格差や経済問題が「黄色いベスト」運動の背景にあること、聖職者による性暴力の可視化により教会の権威が根本的に問いただされていることが、政教分離法が制定された1905年前後のフランスと「共和国原理尊重強化法案」を掲げる今日のフランスという二つの「ライシテの転機」の比較を通して浮き彫りにされました。
報告2(谷垣真理子)では、物理的な「見える暴力」の応酬が発生した香港の2019年大規模抗議活動の経緯と、構造的な「見えない暴力」として解釈されうる香港版国家安全維持法の概要が取り上げられました。大規模抗議活動後の2019年11月の区議会選挙で、抗議活動を支持する「非建制派」は議席を増やしましたが、得票数それ自体は抗議活動に反対する「建制派」とそう大きく離れておらず、香港社会の分断が市民のレベルでも進んでいることが明らかになっています。2020年6月30日に成立した国家安全維持法は、汎民主派関係者の大量逮捕や『りんご日報』閉鎖などをもたらす一方で、中国政府の総体的国家安全観のもとで「一国二制度」の新たな形態が模索されていることを示してもいます。国家安全維持法の言わば底線が探られている現状において、香港出生者が香港総人口の過半数を割り込む日が刻一刻と近づくなか、中国対香港という単眼的な図式にとどまることなく、国際社会での中国の位置というより大きな枠組みで問題を捉え直す必要性が示されました。
報告3(矢口祐人)では、しばしば安易に語られるアメリカと暴力との結びつきを超えて、国民国家アメリカの奥底に不可分な形で組み込まれた根底的な暴力性が指摘されました。犯罪発生率や殺人件数、収監率といった指標は暴力的なアメリカの証左とされますが、こうした数値の背景にはアメリカ社会の成立にまでさかのぼる歴史的経緯があります。報告では、現代アメリカの社会問題を歴史的に把握する試みとして、人種と権力の観点からアメリカ社会の正当性や合法性を批判的に考察するCRT(Critical Race Theory)の議論が紹介されました。アメリカの根幹にある歴史的な「暴力」とそれを隠蔽する現代の「暴力」に対して、BLMの創設者とされるAlicia Garzaや、アフリカ系アメリカ人の再審請求をおこなうEqual Justice Initiativeの活動、そして白人のクリスチャンたちによる人種的連帯の運動は、非暴力による抵抗を通じて、歴史的な「暴力」の制度を根本から変容させることを目指しています。「暴力」は観察し論じるだけの対象ではなく、正されるべきものであり、こうした実践にも目を向けながら社会の不公平や不正義に立ち向かう点に研究活動の社会的意義と役割があることが示されました。
シンポジウムの後半では、二人のコメンテーターと参加者を交えた質疑応答がおこなわれました。
コメント1:早川英明(地域文化研究専攻博士課程・日本学術振興会特別研究員)
コメント2:キハラハント愛(地域文化研究専攻)
コメント1(早川英明)では、三本の報告から取り出された、構造的暴力および、抵抗や抗議の側に付随してしまう暴力という二つの論点に立脚し、早川氏の専門であるレバノンのマルクス主義思想家マフディー・アーミルの思想が解釈されました。そのうえで、ジェンダーやセクシュアリティの問題と宗教的権威の関係、香港の抗議活動内部における政治社会的な構造の理解、抗議現場で生じる暴力に対するアメリカの「非暴力」の活動家たちの態度といった点に関する質問がなされました。
コメント2(キハラハント愛)では、国連および国際法の観点から「暴力」がどのように切り取られているのかが、特に国際人権法、国際人道法、国際刑法の枠組みで紹介されました。また、国家による「暴力」、ジェノサイドや戦争犯罪などの大規模な「暴力」、「保護する責任」のように、国際関係の文脈ではじめて問題としうる「暴力」の様相についても指摘がありました。そしてフランスでの一連の「暴力」と国際社会の取り組みとの関係、香港での「暴力」の主体・種類・被害者の様相、「暴力的な体制」との闘いにおけるjusticeという語の使用について、各報告者に質問が提示されました。
このほか、「見える暴力」と「見えない暴力」を判断する基準、ジハード主義者に対する宗教権力の影響、同性愛処罰の法案に対するローマ教皇庁の対応、右派的主張・左派的主張の転換、ウイグル・チベット・モンゴルの現状などについて参加者から質問が寄せられました。
最後に、「暴力」やそれへの抵抗を理解するうえで地域文化研究はどのような役割をもつのかという質問がありました。各報告者からは、当該地域の十分な知識をもったうえで距離を置いて文脈を適切に理解すること、地域の情報を未加工の状態で取り出してくること、学際的なアプローチやさまざまな時間軸・空間軸のなかで問題を捉えることの重要性、マイノリティの視点からシステムを思考することといった、地域文化研究が有する学問的特徴と、「暴力」の問題に取り組むための地域文化研究の有効性が示されました。
今回のシンポジウムは、フランス・香港・アメリカ、そして中東地域の実例を交え、時間的にも、過去と現在を往復しながら未来にも目線を向ける、有意義な議論の機会となりました。今日、「暴力」の問題は非常に多様かつ複雑で、議論が尽きることはありませんが、本シンポジウムがさらなる議論や実践のきっかけになることを願っています。
司会・文責:藤岡俊博(地域文化研究)
在学生によるリアクション・ペーパーから
本日のシンポジウムでは暴力が社会の中で構造化され、その支配層によって、社会に内在化されるものという共通点があることを理解した。それを前提に私の専門である北朝鮮政治と暴力との関連から小さな考察を試みたい。
北朝鮮政治体制と暴力とはもはや不可分であって、高度に内在化されていると言えよう。3代続く「金王朝」を維持するために政治・社会のあらゆる側面で暴力が所与のシステムとして設置されている。
近年でも張成沢のような政府高官の粛清や金正男といった最高指導者親族の暗殺が報じられた。また市井の人民に対しても、政治体制への忠誠に反する行動をした者を収容する強制収容所の存在、移動の自由の禁止など露骨な暴力が向けられている。
以上のような国家権力からのハードな暴力のみならず、体制への忠誠心を養う教育制度や徹底的な集団主義など国民の精神的自由を奪うソフト面からの暴力も存在する。
一方で、近年、北朝鮮の中で、新たな側面からその社会の暴力性が明らかになっている。それは北朝鮮に暮らす女性を取り巻く環境である。
前提として、李朝以来の儒教的価値観が根付く北朝鮮では男尊女卑の価値観が残滓する。そこでは男性が社会に出て、仕事をする一方、女性は子育てや家事といった家庭内での役割を求められる典型的な男女分業が行われている。
そもそもこの構造が女性に対して暴力的ではあるが、加えて近年、北朝鮮社会に発露する資本主義的な営為の主体が女性になっている点も新たな暴力の発露として考えられるかもしれない。
北朝鮮社会の中で資本主義的な営為が存在すること自体、その体制の根本原理と矛盾する。しかし、その矛盾した営為の主体にならざるをえないのも、男女分業が明確な中で男性が工場などでの「正規労働」を行う必要があり、しかも社会主義制度の行き詰まりのためにその「正規労働」によって、生活するに十分な金銭を得ることができないという背景がある。強固な男女分業と崩壊する社会主義制度の建前の固守のために男性が動員されるがゆえに、実際に金銭を獲得する負担も女性に対して課されてしまっているのである。
暴力は社会の中で構造化され、その支配層によって、社会に内在化される。その上で、北朝鮮の女性を取り巻く環境を見ると、暴力はその社会が持つ矛盾や限界を契機に、マイノリティや弱者に対してより強く作用することがわかる。換言すれば、その社会の脆弱性や停滞が明らかになった時、暴力は従前とは異なる諸相で構造的に社会に内在化されかねないのではないだろうか。(韓国朝鮮/秋圭史)
シンポジウムで取り上げられていた三つの地域における「暴力」のあり方には、それぞれ歴史的な特殊性を踏まえる必要がありながら、一方で、その「暴力」を分析する視点や背景の共通性を見なければならないと感じました。今回の報告は、「暴力」の現れ方と国家、民衆の関係を軸として、それぞれのケースにどのように共通性を見出せるのかを考える上で非常に参考になりました。
今回のシンポジウムの内容としては、どの地域も「国内」における「暴力」のあり方について注目されており、やはり(近代)国家の暴力の独占が暴力の現れ方そのものをいかに規定しているのかという問題と関連づけられなければならないと思います。国家の暴力は正当なものとして捉えられるが故に「見えなく」なっている一方で、そうではない民衆の蜂起は国家・社会にとっての脅威と見做されるということはどの事例においても共通しているといえます。
こうした構造に対して、民衆の側の「暴力」は、「当然」のものや「中立」なものと捉えられてきた国家による暴力を相対化することで対抗してきました。アメリカにおける黒人運動や、香港における民主化を求める運動は、特に差別の問題を明らかにすることで、国家の暴力(およびそれを可能にするより広い構造)の可視化を実践してきたといえます。もちろん両地域における国家の暴力行使のあり方には違いがありますが、何らかの共通性・関連性を見出そうとする動きは重要だと考えます。中国の「専制」を批判するアメリカでも依然として黒人に対して不当な直接的暴力が振るわれ、制度がそれを追認するといったことが起きていますが、国家の暴力のあり方を横断的に捉える視座は、「民主」か「専制」なのかを決定的な差異とし、双方を隔絶されたものとして捉えるのが適切であるのかを問うことにつながると思われます。
他方、フランスにおけるムスリムへの脅威視、「黄色いベスト」、聖職者の性暴力の可視化などの動きについては、狭義の国家(政治)の次元とは区別された意味での社会における暴力の現れ方について取り上げられていました。ムスリムのテロリズムと「黄色いベスト」は実際に暴力を伴う「運動」であるといえるかもしれませんが、そうしたものを分析する上でも、その捉えられ方と力関係に注目することが重視されていました。例えばムスリムの「暴力」を取り上げる際に、むしろ既存のイスラモフォビアや差別の力関係を強化し、正当化するはたらきが作用しうるといったものです。「黄色いベスト」運動についても、同様に経済的な格差などに対する問題提起であることが無視される可能性もあるという点で、上記の視座が必要とされています。これらは構造的な不平等などの問題を「不可視化」することでこそ、蜂起を単に「暴徒」「狂信者」によるものとし、より一層国家の正当化を必要だと思わせることになるのだと思います。聖職者の性暴力の可視化については、暴力がよりミクロな視点から捉えられてきたと同時に、その背景として宗教的な権威の影響力が従来と比べて弱まっていることが紹介されていました。他の事例についても言えることですが、ミクロな視点から見た暴力も、国家と宗教の関係がどのように再編されているのかなど、国家の及ぼす力とどのように関連性があるのかを問うことが重要であることが示されていました。
シンポジウムにおいて示されていた、さまざまな暴力を分析するための視点は、どれも特定の地域の分析にとどまらないものであり、今日において各地域にどのような共通性が見出せるのかを考える上で非常に興味深いものでした。シンポジウムで紹介されていた地域以外にもいわゆる「ポピュリズム」現象が多発しているなかで、こうした観点はよりいっそう重要性を増しているのではないでしょうか。
今回の報告を踏まえて、国際的な背景との関係から暴力のあり方の共通性・関連性、また暴力が不可視化される構造について、自身の研究においても意識する必要があると考えました。(日本/苅部真也)
私は今回のシンポジウムで先生たちのご発表を聞いて、人間の利己性と暴力の問題、特にコロナ・パンデミックが人間関係の暴力化に及ぼす影響について考えてみた。コロナウイルスの強力な伝染性により、人々は自分が出会う全ての人々を潜在的な伝染源とみなし、不信を抱くようになった。また、ウイルスに感染した人や集団を病菌と同一視して敵視する。国家も国境を閉ざし、外国人の出入を遮断して人々を統制し監督する。
人々は内部の危険を克服するためにいつも外部から敵を作る。マキャヴェリによると、幸運は君主を偉大にするために敵を作る。君主は敵というその梯子に乗って飛翔するが、賢明な君主はそのような敵対感情をわざと助長したりもするということだ。
しかし、必ずしも政治指導者の術策ではなくても、このような排他性は人間の利己心が作る自生的な現象なのかも知れない。人々は分離不安から逃れるために集団に所属したがる。そこで、特定の集団に所属することで感じるその安堵感が他集団からの脅威に反応し、葛藤と暴力の形に発展するのではないかと考える。コロナの事態こそ、このような現象を煽るのではないか? 私はコロナ以降に我々人類が全世界的に、キハラハント先生がおっしゃった「不可視の暴力」という形で、よりたやすく暴力に流されるようになったと考える。
個人と自己集団を超えて全体を考えるべきだ。特にパンデミック・ウイルスの感染性を考えると、一個の国家は直面した目前の困難から早く離れることも重要だが、全世界的な次元での利他的な協力がより必要である。いま、選挙に依存するしかない民主主義社会の宿命と言えるかも知れないが、各国ではポピュリズム政策のみが乱舞している。これは結果的に個人・集団間の暴力、及び国家間の戦争を胚胎する。このような傾向こそ谷垣先生がおっしゃった制度的な「見えない暴力」の一つではないかと考える。
私だけの安寧、自己手段だけの安定、自己国家だけの繁栄を追求する人間の利己心が、人間関係と国家関係を歪曲して、結果的には暴力として発現されるのではないかと懸念される。私だけを考える利己心を超えて、他人と共生し共存する利他性を回復せよ。目の前の利益よりも未来への影響を考慮し、一国を超えて世界人類全体を共にする人類愛を志向する態度が必要である。(アジア/姜旼志)
シンポジウム全体を通して、早川先生のおっしゃった「付随する暴力」に表されるような、暴力とその連鎖への視野が自分の中で広がったように思います。部分的なことでは、矢口先生の発表において、暴力に立ち向かう非暴力的な行動を支えるキリスト教の精神が紹介されましたが、その宗教性がどれほど意識されているのか、アメリカ内で人々が信仰する他の宗教にはこの精神がどう受け止められるのか、気になりました。また谷垣先生の発表はシンポジウム後に『香港画』をみたことで理解が深まりました。
次に発表を拝聴しながら考えた歴史について書きます。伊達先生が少し触れられ、矢口先生の発表とも通ずる、歴史に「暴力」の根幹を探るという手法の可能性が印象的でした。谷垣先生が発表内で共有された動画をみている時にも、その音楽、言葉遣い、戦う民衆の描き方が、例えば『レ・ミゼラブル』などの映画と(あくまでも直感的なレベルではありますが)あまりに似ていることに驚き、同じく歴史の重要性を感じました。特に、様々な「暴力」自体への見方に関して、感情史が貢献できるところは多いのではないでしょうか。時と場所、立場などが違えば、ある行為が「暴力」とされる理由は異なるでしょうし、そもそも「暴力」とは捉えられていないかもしれません(例:子どもへの体罰)。「暴力」をふるった者によりその正当化に使われる言葉、またふるわれた側が使う語彙の分析や、どんな場面でどのように「暴力」がふるわれたかというパフォーマティブな観点、あるいは「感情の共同体」「感情体制」といった考え方など、感情史には、そこに何らかの「感情」が含まれていないとしても、ある「暴力」を考える方法として参考にできるものが多いように思うので、これから探っていきたいです。(フランス/土方咲)
昨年までの公開シンポジウム情報はこちらから